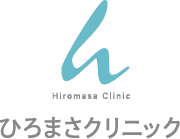- HOME
- 心筋梗塞
心筋梗塞とは?

心筋梗塞は、心臓の筋肉に血液を送る冠動脈が詰まり、その先の心筋組織が酸素不足で壊死する病気です。病気が進行すると全身の血流が滞り、意識消失や呼吸困難などの重篤な症状を引き起こすほか、時に命にも関わります。発症からいかに早く治療できるかが、良好な予後のための鍵となります。
心筋梗塞は狭心症から発展することもありますので、胸痛や胸の圧迫感などが頻繁に起こる場合には、早めの対策が重要です。神戸市東灘区・御影のひろまさクリニックでは、循環器専門医による診察と診断で心筋梗塞の発症を未然に防ぎます。不安な症状がある方は、一度ご相談ください。
心筋梗塞の症状
心筋梗塞の典型的な症状は強い胸痛です。狭心症による胸痛は、安静にしていれば数分から15分以内に治まりますが、心筋梗塞の場合は安静にしても30分以上持続します。以下のような症状が現れたら心筋梗塞の可能性を考え、すぐに救急車を呼びましょう。
- 胸の激しい痛み、圧迫感、締め付け感
- 胸痛が左肩、左腕、顎、背中、上腹部へ広がる
- 冷や汗、息切れ
- 吐き気、嘔吐
- 呼吸困難
- 意識障害
など
心筋梗塞の前兆
心筋梗塞を発症する1週間~1か月ほど前から、軽い胸痛や圧迫感などの狭心症の症状が見られることもあります。痛みは自然に治まることが多いですが、頻繁に胸痛が起こったり、夜間や安静時にも痛みが生じたりする場合には、心筋梗塞を疑って早めに受診してください。
心筋梗塞の原因

心筋梗塞の主な原因は、冠動脈の動脈硬化です。長年かけて冠動脈の内側にコレステロールが蓄積し、プラークと呼ばれる隆起ができます。このプラークが破裂すると、血小板が集まって血栓を形成し、血管が完全に閉塞して心筋梗塞を発症します。
動脈硬化を引き起こす主なリスク要因には以下があります。生活習慣に起因するものが多く、複数の要因が重なれば、その分だけ心筋梗塞のリスクが高まります。
- 高血圧
- 脂質異常症
- 糖尿病
- 喫煙
- 肥満
- 運動不足
- ストレス
- 家族歴(家族に狭心症の方がいる)
など
心筋梗塞の検査
心筋梗塞の治療は時間との戦いですので、以下の検査を迅速に行います。
心電図
心臓の電気信号を測定し、心筋梗塞で見られる特徴的な波形変化(ST上昇やQ波形成など)を確認します。発症直後からこれらの変化が現れるため、診断の第一歩となります。
血液検査
心筋の細胞が壊死すると、トロポニンやCK-MB(クレアチンキナーゼMB)などの酵素が血液中に放出されます。これらの上昇は心筋梗塞を示す重要な指標ですので、血液検査によって迅速に測定します。
心エコー
超音波を用いて心臓の動きの異常や機能などを評価します。詰まった血管の部位をある程度予想できるので、治療計画を立てるためにも重要な検査です。
心臓カテーテル検査
専用の細いチューブ(カテーテル)を足や腕の血管から挿入して心臓まで到達させ、冠動脈の状態を直接観察します。そのままカテーテル治療へ移行することもできるため、急性心筋梗塞では特に重要な検査です。
※搬送先の病院で実施されます
心筋梗塞の治療
発症直後の心筋梗塞の治療では、血管の詰まりをいち早く解除し、心筋の壊死を最小限に抑えることが目的となります。血流が途絶えてから心筋の壊死が始まるまでの時間は20分ほどですので、発症後は一刻も早い処置が必要です。
搬送先の病院での治療(緊急治療)
病院への搬送後は、詰まった冠動脈を再開通させるための手術(カテーテル治療や冠動脈バイパス手術など)を行い、心筋の壊死を食い止めます。
クリニックでの治療
心筋梗塞の緊急治療を終えて退院した後も、再発予防と心機能の維持・改善のための治療が必要です。定期的な通院と検査、お薬の継続的な服用、生活習慣の改善を通じて、再発予防と健康的な生活を目指しましょう。
当院では退院後の患者様への丁寧な経過観察を行いつつ、スタッフとともに行う心臓リハビリテーションも行っております。リハビリの専門家による適切な運動療法により、再発予防とQOL(生活の質)の維持・向上をサポートいたします。